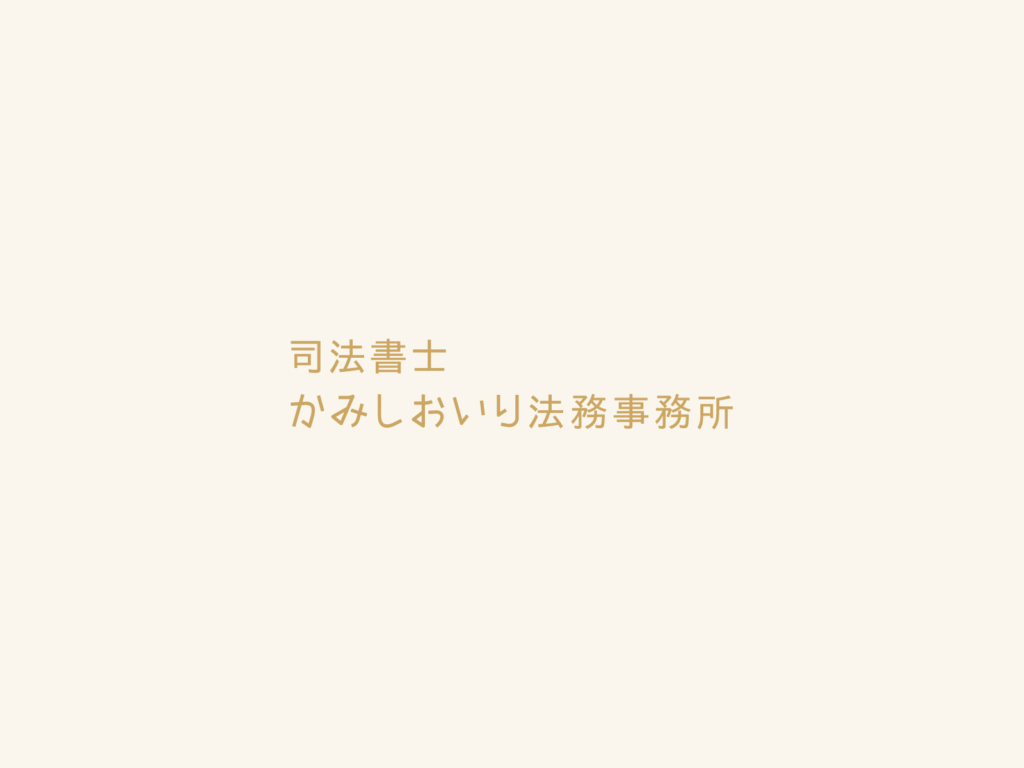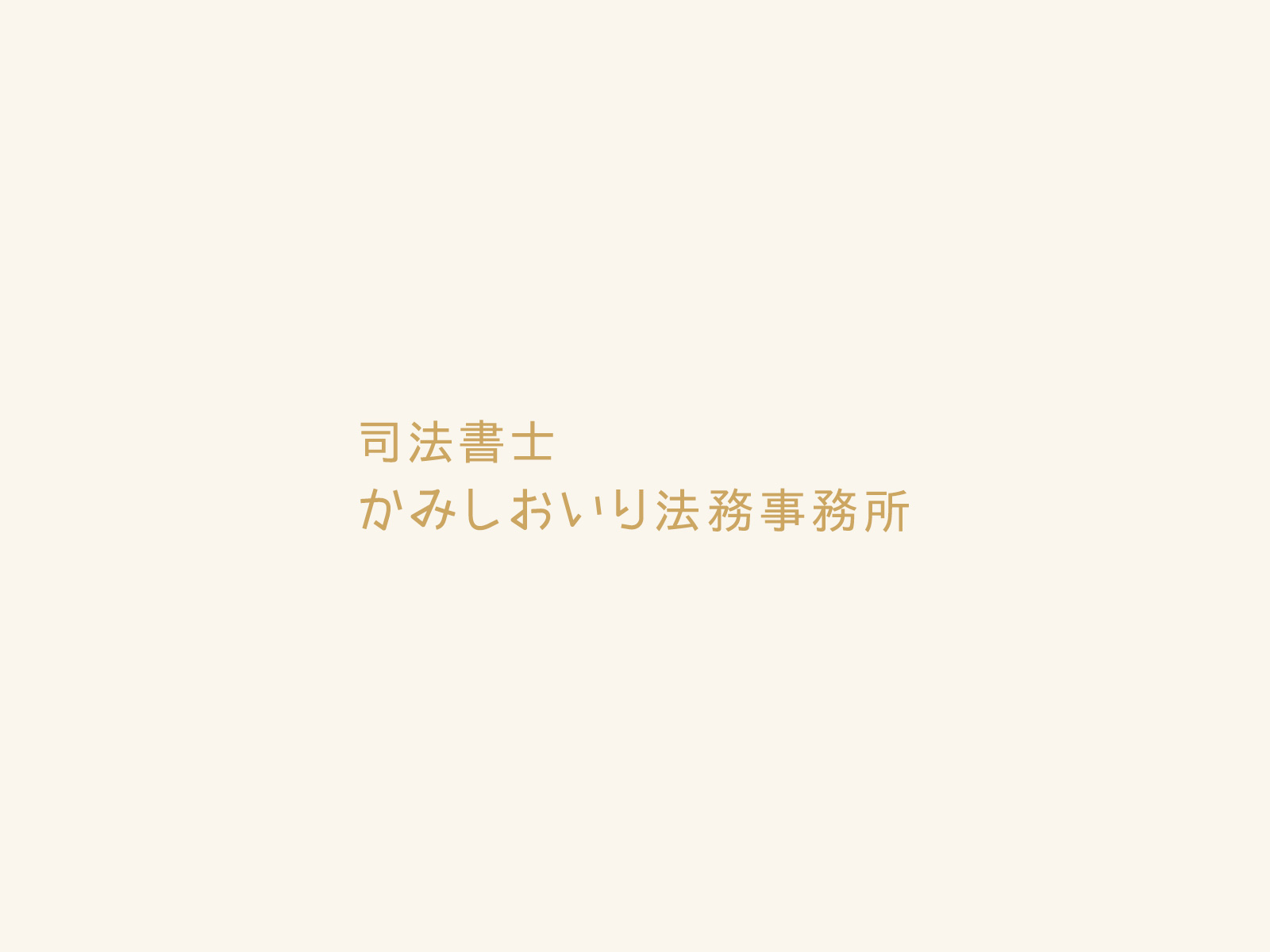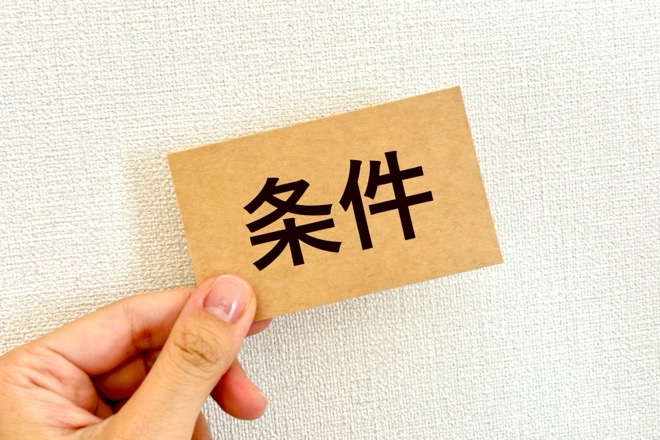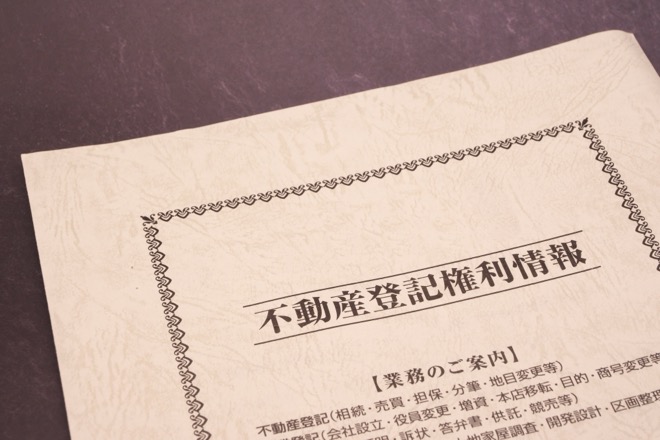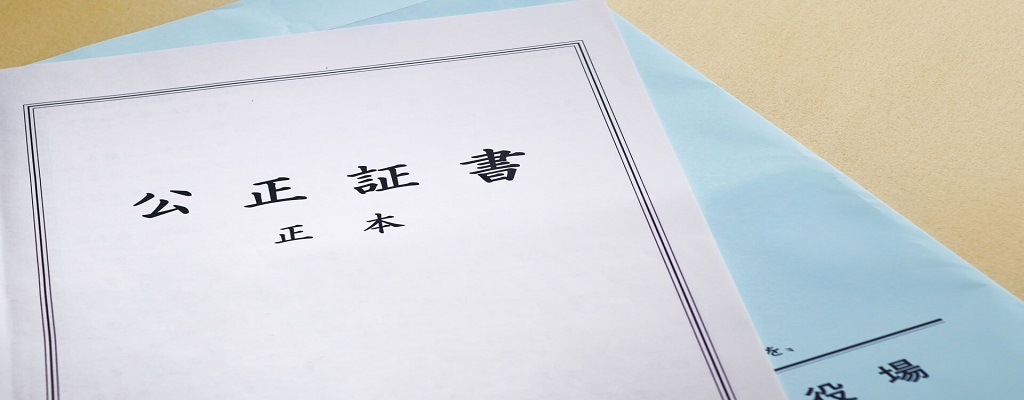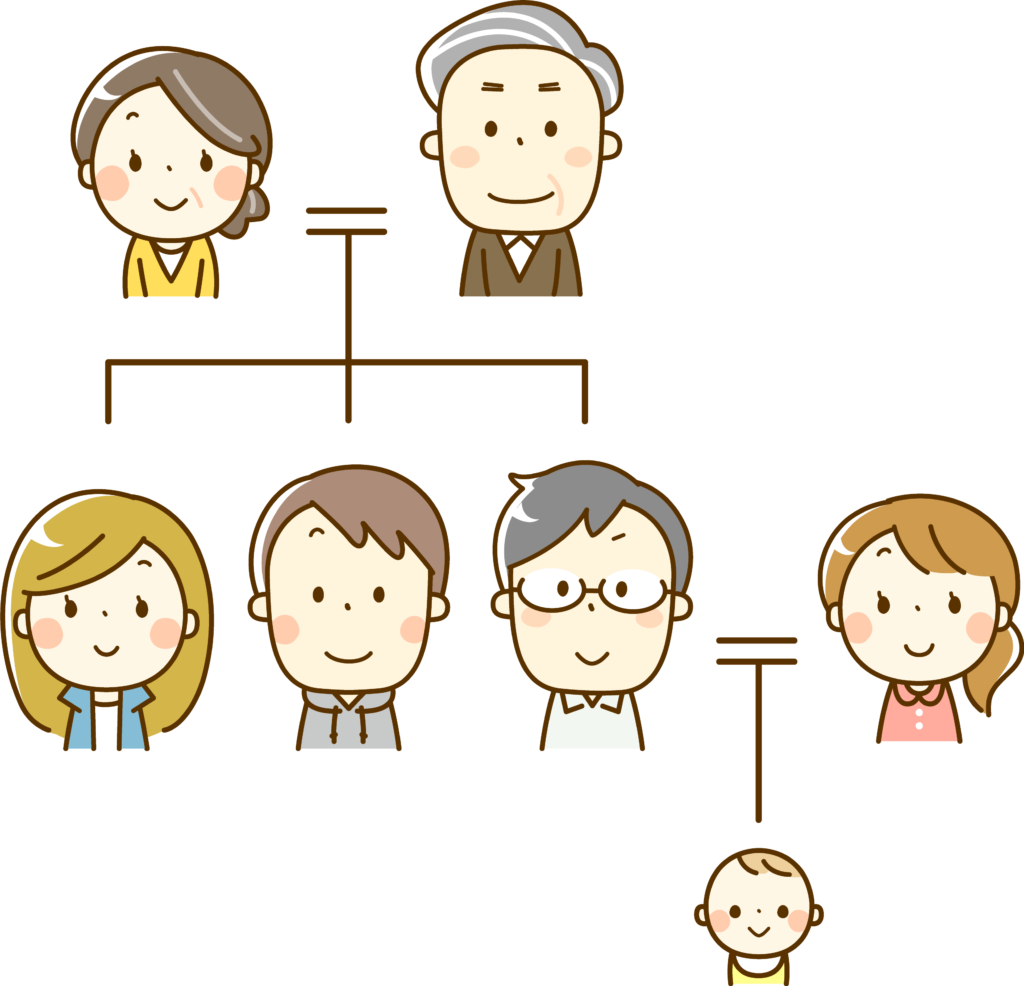-

【相続 相談解決事例】不動産に古い法人名義の根抵当権が付いていたケース
令和6年4月1日からの相続登記義務化に伴い、相続に関するご相談がこれまで以上に多くなっています。今までは亡くなった方名義のまま放置していた不動産を放置しても罰則がありませんでしたが、法改正後は放置すると過料の対象になります。その影響で、... -

株主や取締役が死亡したときの手続や相続の手順
株式会社や合同会社は、一般社団法人のように複数人数での設立が要件となっていないため、1人で立ち上げることができます。近年では人口減少、事業の成り手不足、コストカット、定年の引き上げなどにより、小規模な個人事業主が唯一の株主かつ取締役とし... -

成年被後見人、被保佐人、被補助人死亡後の死後事務手続と財産引継ぎ、どこまでが元後見人の仕事なのか
成年後見制度を利用していた本人が死亡すると、後見人(保佐人・補助人)としての業務は終了し、法定相続人に対して引継ぎを行い後見業務が終了します。本人に配偶者、子供がおり、本人のご存命時から連絡を取れる関係性であれば問題にはなりませんが、近... -

Webメディア「円満相続ラボ」とパートナー提携しました。
相続業務に関して、弊所は「円満相続ラボ」とパートナー提携をいたしました。https://enman-souzoku.co.jp/media/partners/円満相続ラボは、「相続・終活が分かる、見つかる、解決する」をコンセプトに立ち上げたWebメディアです。「争う『争続』をなくし... -

保佐人とは?業務内容、後見や補助との違い
認知症などで判断能力が低下した方の財産と権利を守るための方法として、成年後見制度が存在します。この成年後見制度を利用すると、ご本人には法律上定められた代理人が選任され、法定代理人がご本人の財産と権利を守ることになります。成年後見制度には... -

相続放棄が無効になる場合とは?
相続放棄とは、亡くなられた方に関する債権債務、不動産、預貯金、株式など、相続財産と呼ばれるすべての財産を放棄し、法律上はじめから相続人ではなかったことになる法的手続です。相続放棄は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産すべてを放棄するこ... -

養子縁組とは?普通・特別の違いや条件、相続税対策を解説!
養子縁組は、血縁関係にない人々が法律上の親子関係を結ぶ制度です。この制度は法律上の親子関係を生じさせるだけでなく、相続税対策としても重要な役割を果たしています。しかし、その手続きや種類、さらには税務上の考慮事項には特有の複雑さがあります... -

相続で親族間の紛争を避けるための対策と対処法
親族間の相続における争いは、それまでの関係を一変させ、今後の親族間の関係をも悪化させてしまう可能性があります。相続人同士の争いは、ほぼすべてが感情的なものか金銭的なものを原因として起こりますが、適切な対策と事前の準備を行うことで、これら... -

相続放棄前の債権債務調査の方法は?どんな手段がある?
親、兄弟姉妹、子供、叔父叔母など親族が亡くなった場合、必ず「相続」の問題が生じます。相続が発生して自分が相続人であることを認識したとき、まず第一に「財産がいくらあるのか?自分以外の相続人は誰なのか?相続するのか放棄するのか」が気になる方... -

相続登記の義務化とは?手続を早めに行うメリット
相続登記とは、不動産を所有していた個人が亡くなった場合に、故人から相続人へ不動産の名義(所有権)を移転させる登記手続のことです。令和6年(2024年)4月から法改正により相続登記が義務化され、今までのように亡くなった方名義のまま不動産を... -

終活身辺整理の秘訣 快適な生活のためのステップ
近年、お一人様や核家族化が一般的になり、ご自身に万が一があったときのことをすぐに共有、相談できる相手が減っている方が多くなっています。そのような方々のために、「終活」という活動が注目されています。終活身辺整理は、自身の生活を快適にし、残... -

デジタル遺品、デジタル遺産とは?
ネットが普及した現代では、デジタル遺品と呼ばれるものが注目されています。デジタル遺品とは、現物の遺品ではなくデータとして所有していた遺品、もしくはデータ情報が含まれている遺品のことを指します。デジタル遺品やデジタル遺産は現物の遺品と異な... -

相続などで使用する戸籍の取得が簡易になる「広域交付」とは
主に相続の手続きなどで使用する戸籍は、本籍地を置く市区町村の窓口か郵送で請求しなければならないため、日中お忙しい方や不慣れな方、本籍地が遠方の方にとっては大きな負担です。そこで、戸籍法の改正がなされ、令和6年(2024年)3月1日から戸... -

相続税評価とは?計算方法など
一定の財産を有している人が亡くなった場合、相続税がかかることがあります。相続税の算定をするときに、亡くなった方名義の財産を金銭的価値で評価しますが、土地や建物などの不動産、株式、預貯金、保険、自動車、家財道具など、金銭で評価するために少... -

住所変更や結婚で名字が変わったら遺言書の修正が必要?
公正証書遺言書は遺言者の住所、氏名、生年月日を記載することで、遺言書を作成した本人を特定します。公正証書遺言書を作成したあと、住所や氏名に変更があった場合、遺言書を修正したり、変更する必要があるのでしょうか?遺言書の修正の必要性や、遺言... -

遺言書がある場合は遺産分割協議が不要?
有効な遺言書が作成されているとき、相続手続は原則として遺言書に沿って行われます。そのため、相続人の全員による話し合いである遺産分割協議が不要になりますが、遺言書があっても遺産分割協議が必要になることもあります。遺言書がある場合は遺産分割... -

生前贈与と相続遺言での贈与はどちらが安い?費用、手続、税金など比較
家、土地、貴金属、現金、自動車などの財産を相続人や第三者に渡す方法は、主に売買・贈与・相続の3つがあります。その中でも、土地や建物については、生前から相続人の誰かに贈与しておきたいと考える方が多くおられます。しかし、本当に生前贈与を選択... -

相続分の譲渡とは?相続放棄との違いや注意点
相続には「相続分の譲渡」という手続が存在します。相続分を譲渡すると、譲渡を受けた方が法定相続人と同じような権利を持つことになります。相続分の譲渡は上手に活用することでメリットがありますが、税金面や手続面、相続人同士のトラブルの観点からは... -

認知症の方名義の不動産を売却処分する方法
日本にいるほとんどの人にとって最も大きな資産は不動産です。不動産を売却処分することは民法に規定された売買契約に該当し、非常に大きな金額が動くため不動産の名義人本人の明確な意思、判断能力が必要です。不動産の名義人が認知症などで判断能力が低... -

遺言で自分の財産を寄付するには?生前、死亡時の寄付方法と注意点
自分が亡くなったときに財産を寄付したいというご相談が増えています。生前、死亡時に寄付をする方法や注意点を解説します。【寄付が増えている理由】核家族化や少子高齢化により、身寄りがない方や親族と疎遠になっている方が増えています。それとともに... -

遺族に負担をかけないための生前整理
【生前整理とは?】生前整理とは、自身の死後に遺族が直面する問題や負担を軽減するため、生前に自分の物や財産を整理する行為です。生前整理は物理的な整理と、精神的(情報などの)整理があります。物理的、精神的いずれにしても自分一人で整理すること... -

成年後見人ができること。保佐、補助との違い
成年後見人とは本人の代わりに法律行為などを行う法定代理人です。成年後見人ができること、できないこと、保佐人や補助人との違いを説明します。【成年後見人とは】成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した本人のために、財産管理や身上監護を行... -

相続における養子と実子、婚姻外の子の相続権の違い
子どもが相続人になることは広く知られていますが、「子ども」には血の繋がった実子のほか、養子縁組によって成立した法律上の子である養子も含まれます。また、実子は血縁関係のある子どものことですので、婚姻外の相手との間にできた子、前妻前夫との間... -

もめやすい遺言書の内容や特徴
遺言書は亡くなった方の最期の法的な意思表示であり、有効な遺言書があれば相続手続きは遺言書に従って行います。しかし、遺言書は内容によっては相続人同士がもめてしまうきっかけになることがありますので、書き方には注意が必要です。相続専門の司法書... -

まだ生まれていないお腹の子に相続権がある?
まだ生まれていないお腹の中の子ども(胎児)は相続権があります。胎児に関する相続の手続や考え方、注意点などを解説します。【胎児の権利能力】権利能力とは、契約の当事者になる、権利を得る、または義務を負うなどの権利義務の当事者になる能力のこと... -

相続人がいない場合の財産はどうなる?
相続が発生したとき、民法で相続人になる方と順序、相続できる割合を定めています。しかし、核家族化、少子化、生涯独身率の上昇した現在では、法律上の相続人がいない場合もあります。相続人がいない場合の財産がどうなるのか、詳しく解説します。【法定... -

遺言書や遺産分割協議書に書いていない財産があるとき、どうなる?
遺言書や遺産分割協議書に書いていない財産が後から見つかった場合や、書き漏らしてしまった財産がある場合、遺言書や遺産分割協議書が全体として無効になることはありません。しかし、書いていない財産は別途個別のケースに応じて対応をすることになりま... -

銀行の遺言信託は高い?本来の遺言信託との違い、手数料、解約方法、メリットデメリット
最近、銀行をはじめとする金融機関が店頭やCMなどで「遺言信託」と謳ったサービスを案内していることが増えました。しかし、銀行が案内している遺言信託は、法律上の意味でいう遺言信託とはまったく異なるサービスであり、誤解を生む表現ですので注意が必... -

譲渡所得税とは?不動産を売却したときに税金がいくらかかるのか
不動産を購入時の価格よりも高い金額で売却できた場合、譲渡所得税がかかることがあります。【譲渡所得税とは】土地、建物、株式、貴金属などの資産を売却して得た利益に対してかかる税金です。本記事では土地建物の不動産について解説します。【譲渡所得... -

遺留分を主張した、請求された場合の相続税
遺留分とは亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、「遺産を最低限取得できる権利」のことです。相続税は、相続が起きてから10か月以内に税務署に申告をすることになり、財産の取得割合に応じて相続人が申告と納税をします。遺留分を主張...
兵庫県司法書士会所属
神戸の相続・遺言相談所