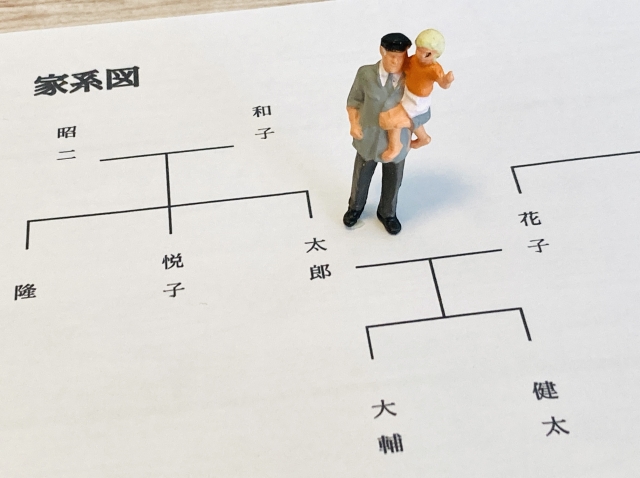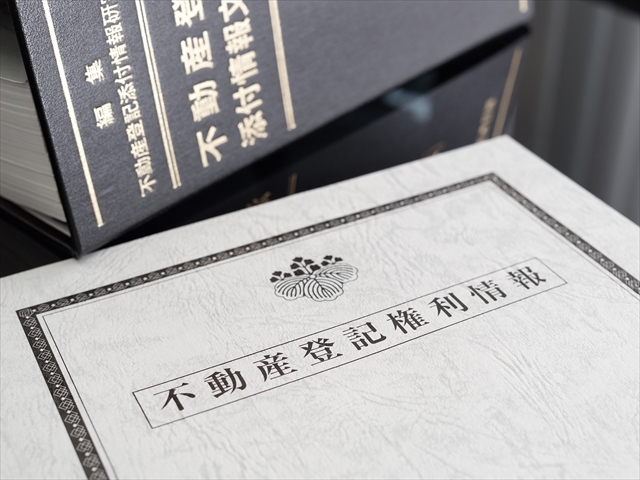養子縁組は、血縁関係にない人々が法律上の親子関係を結ぶ制度です。
この制度は法律上の親子関係を生じさせるだけでなく、相続税対策としても重要な役割を果たしています。しかし、その手続きや種類、さらには税務上の考慮事項には特有の複雑さがあります。
ここでは、養子縁組の基本から、普通養子縁組と特別養子縁組の違い、さらには相続税対策としての養子縁組を行う際の注意点について詳しく解説します。
養子縁組とは?

養子縁組は、血縁関係にない他人同士が法的に親子関係を築くための手段です。
この制度は、子供に恵まれない家庭の家系を維持するためや、後継者を設けるために、日本では古来から広く利用されてきました。
養子縁組の種類
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組と呼ばれる2つの種類があり、それぞれで利用できる条件や意味合いが大きく異なります。
普通養子縁組
「養子縁組」と聞くとまずほとんどの場合は普通養子縁組を指します。
普通養子縁組は一般的な養子縁組の形態で、養親と養子が法律上の親子関係を成立させつつ、一方で養子は実の親とも親子関係を保持します。
普通養子縁組では、養子は実親とも養親とも親子関係にあり、主に養子が成人である場合に用いられます。
特別養子縁組
養子縁組の中には、稀に「特別養子縁組」を結んでいる養親、養子がいます。
特別養子縁組を結ぶと、養子は実の親との関係を断ち切り、養親とのみ親子関係が成立します。
特別養子縁組は、15歳未満の養子に適用され、養子が未成年である場合や、養子が実親から虐待などを受けている場合にに特に有効です。
相続税の観点から
相続が発生すると、相続財産が相続税基礎控除を上回っているとき(相続財産額>基礎控除額)のとき、相続税が発生する可能性が高くなります。
相続税の基礎控除は、「相続人の数×600万円+3000万円」で求めることができます。
つまり、養子縁組を利用することで法定相続人が増えるため基礎控除額が大きくなり、結果として相続税の負担を軽減する効果があります。
しかし、この制度を利用する際には、税務調査によって節税目的の養子縁組と判断されないよう、適切な手続きと正当な理由を備えて行うことが重要です。
養子縁組の条件
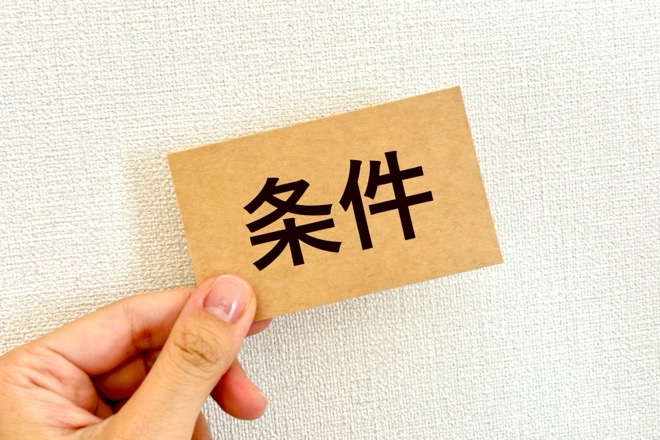
養子縁組は、法的な親子関係を築く手段であり、さまざまな形態があります。それぞれの養子縁組には特有の条件が設定されています。普通養子縁組と特別養子縁組の条件を詳細に解説します。
普通養子縁組の条件
普通養子縁組は、養子が実親との親子関係を維持しながら養親と法律上の親子関係を築く方法です。以下がその主な条件です。
- 養親は成年者であり、20歳以上または結婚歴があること。
- 養子は養親より年少であること。
- 養親と養子双方が養子縁組に同意していること。
- 養子が15歳未満の場合、法定代理人が同意すること。
- 養親や養子が結婚している場合、配偶者が同意していること。
- 未成年の養子を迎える場合は家庭裁判所の許可を得ること。
- 養子縁組届を養親または養子の本籍地か住所地を管轄する市区町村役場に提出すること。
普通養子縁組では、養子が実親、養親双方と親子関係を維持するため、相続が発生したとき、実親、養親それぞれの相続人として財産を取得する権利があります。ただし、権利と同様に実親、養親双方から義務や債務を承継します。
条件は比較的柔軟で、多くの場合に適用されますが、年齢の制限には注意が必要です。
特別養子縁組の条件
特別養子縁組は、養子が実親との法的な繋がりを完全に断ち切り、養親とのみ親子関係を築く方法です。
以下がその主な条件です。
- 養親となる者が夫婦で共同で養子縁組すること。
- 夫婦の一方が25歳以上、もう一方が20歳以上であること。
- 養子となる者が原則として15歳未満であること。
- 実親の同意があること。ただし、養子の利益を著しく害する事由がある場合は同意は不要。
- 特別養子縁組を請求してから6ヶ月以上監護していること。
- 家庭裁判所からの許可を得ていること。
特別養子縁組は、主に実親が何らかの事情で子供を育てることが困難な場合に、子供の権利や生命を守るための手段として用いられます。特別養子縁組により、養子は新しい家族(養親)と法的な親子関係を成立させ、同時に実親との関係を消滅させることができますので、安定した家庭環境を得ることが期待されます。
未成年者を養子縁組とする場合について
未成年者養子縁組の手続
家庭裁判所の許可
未成年者を養子とする場合には、市区町村への養子縁組の届出の前に、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
ただし、養子が、配偶者の子、又は孫などであれば、家庭裁判所の許可は不要です。
養子縁組で相続税対策を行う時の注意点

相続税における基礎控除額は以下のとおりです。
相続税の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人
つまり、法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円も増える計算となります。
相続税は、相続財産の価額から基礎控除額を差し引いた金額に所定の税率をかけた金額となるため、基礎控除額が増えればその分に応じて相続税負担の軽減につながります。
養子縁組で相続税対策を行う時の注意点
養子縁組をすることで相続税対策としてのメリットがありますが、その一方でデメリットもあります。
養子縁組で相続税対策を行う時には以下の注意点に気をつけましょう。
養子縁組で孫を養子にした場合は相続税の2割加算の対象となる
養子となる人に子供がいた場合、養子縁組前に生まれた子は代襲相続の対象外となる
子供の配偶者を養子にした場合は後々に家族トラブルへと発展する可能性がある
税務調査によって節税目的の養子縁組と判断された場合は法定相続人と認められない可能性がある
また、養子縁組をすれば相続税の基礎控除が無制限に認められるわけではなく、人数の制限があります。
(1)被相続人に実子がいる場合
法定相続人に含める養子の数は、1人までです。
(2)被相続人に実子がいない場合
法定相続人に含める養子の数は、2人までです。
ただし、例外として以下のケースでは、制限なく実子として取り扱われます。
- 特別養子縁組により被相続人の養子になった
- 被相続人の配偶者の実の子どもで被相続人と養子縁組をした養子
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた養子で、かつ被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実子、養子または直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、その子どもなどに代わって相続人となった直系卑属(子どもや孫)
税務調査で節税目的と判断された場合
養子縁組が純粋に相続税の節税目的で行われたと税務当局に判断されると、その養子は税務上は法定相続人として認められない可能性があります。そのため、養子縁組を検討する際には、相続税の節約だけでなく、他の正当な理由があることを確認し、適切に記録しておくことが重要です。
特別養子縁組は、養子となる子供の最善の利益を目的とし、新たな家族関係の構築を通じて子供の福祉を増進することを目指しています。したがって、この制度を検討する際には、養子となる子供にとって最良の選択肢であるかどうかを慎重に考慮し、適切な手続きを確実に行うことが求められます。
専門家のアドバイスも活用し、家族関係を大切に行えるようにすすめていくことをおすすめします。