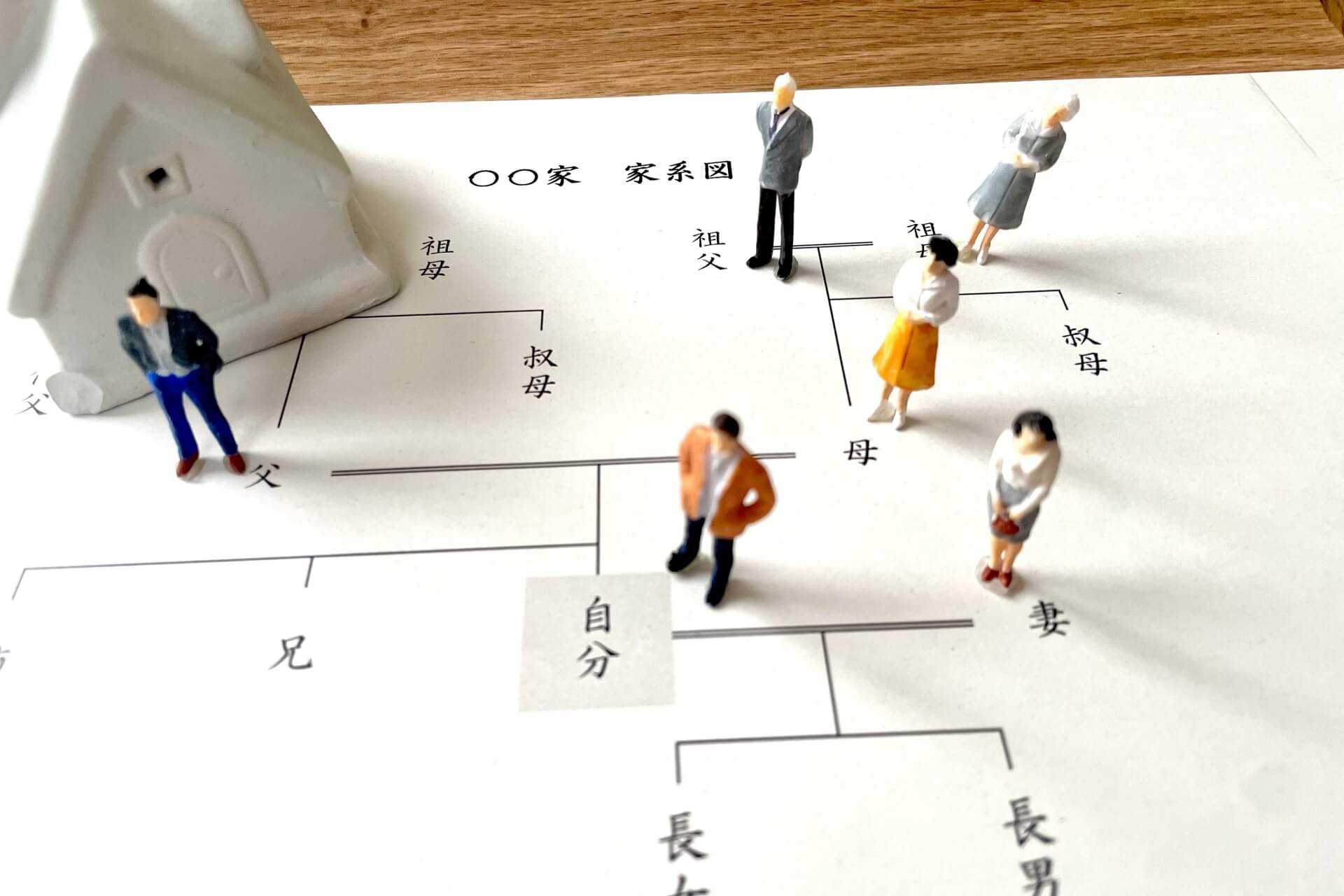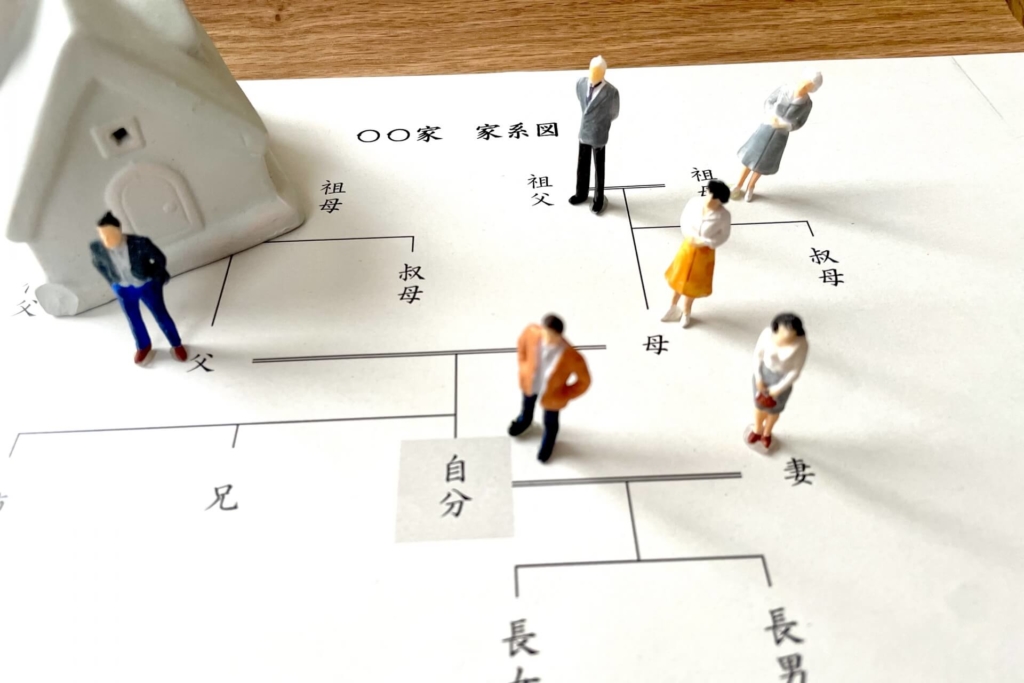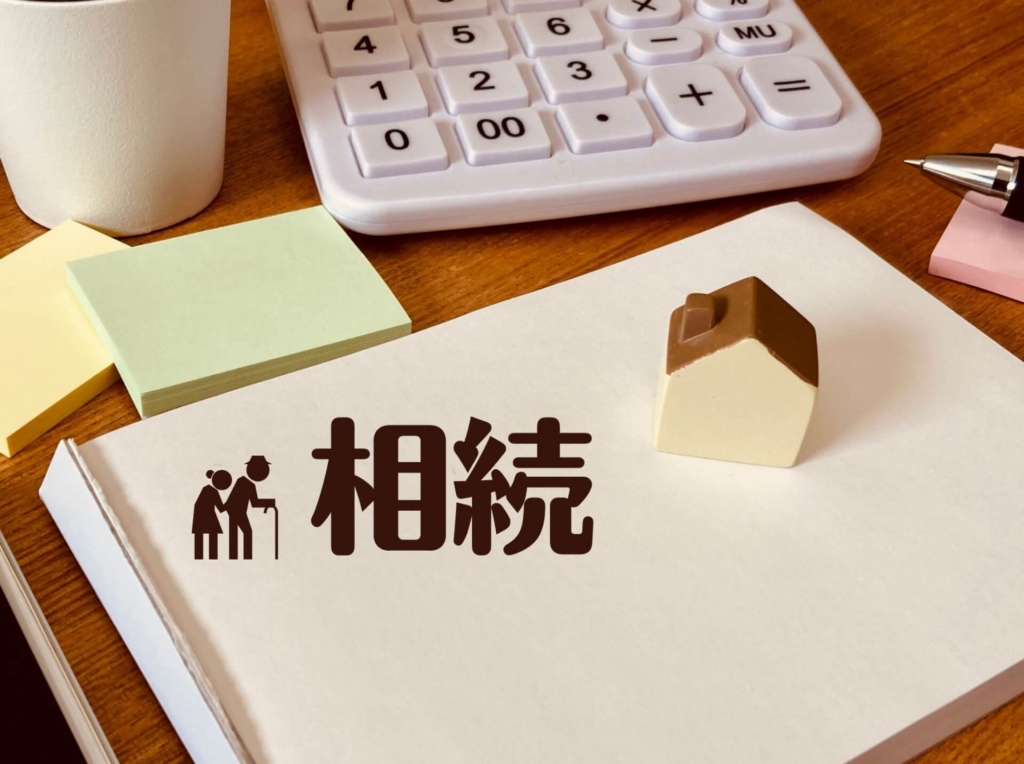相続が発生したとき、民法に定められた法定相続人が法定相続分を取得することになります。
しかし民法には相続人の欠格、相続人の廃除という規定があり、法定相続人が除外される制度があります。
相続人の欠格について、適用されるケース、欠格にする方法、注意点などを解説します。
相続人の欠格とは
相続人の欠格とは、相続人が亡くなった方(被相続人)に対して不法行為などを用いて権利を侵害したときに、強制的に相続人から除外される制度です。
具体的には次の4つの場合が欠格事由に該当します。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
自分が相続に関して優位になるように、被相続人、先順位の相続人、または自分と同順位の相続人を死亡させる等をしたことで刑に処せられた人は欠格事由に該当します。
(2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
被相続人が殺害されたにもかかわらず、殺害者を告発しないときは欠格事由に該当します。
ただし、認知症などで判断能力が低下していたり善悪の判断ができない人は欠格事由とはなりません。
また、殺害者が自分の配偶者や直系血族であるときは、複雑な私的感情や家庭環境が影響したり、周囲に知られたくないという感情が働くことが考えられるため、告発しなかったとしても欠格事由とはならないとされています。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更した者あるいはそれらを妨げた者
脅迫や詐欺を用いて被相続人に遺言を書かせたり変更や撤回させる、もしくはそれらの行為を妨害した場合は、欠格事由に該当します。
(4)被相続人の遺言書を変造、偽造、隠匿、破棄した者
被相続人の遺言書を改変してしまう、隠したり捨てた者は欠格事由に該当します。
相続人の欠格事由に該当する可能性がもっとも高いのは、(3)と(4)に記載した遺言書に関する相続人の行為です。
相続人の欠格になるとどうなるのか
相続人の欠格事由に該当すると、相続権を失います。
ただし、欠格事由に該当した相続人に子供がいる場合は、代襲相続人として法定相続分を取得します。
相続欠格は届出が必要?
相続欠格に該当すると、自動的に相続権を失いますので、届出は必要ありません。
相続欠格は戸籍に記載される?
相続欠格に該当しても戸籍に記載されません。
相続欠格に関する公的な証明書はある?
相続欠格には公的な証明書がありません。
しかも、先述のように戸籍にも記載されないため、第三者からみて相続人が欠格者なのか否かは判断できません。
相続欠格に該当する相続人がいる場合は、欠格者に該当した人が「相続欠格に関する証明書」に署名押印をすることになりますが、相続欠格者である書類に自発的に署名押印する人は多くありませんので、たいていは裁判所に対し相続権に関する確認訴訟を申立てます。
相続人の廃除との共通点と違い
相続欠格と相続人廃除は一覧にすると次のようなとの共通点、違いがあります。
| 相続欠格 | 相続人廃除 | |
| 要件 | ・被相続人や相続人を死亡させ(ようとする) ・詐欺や脅迫で遺言書を作成変更撤回させ、またはそれらを妨害する ・遺言書を変造偽造破棄隠匿する | ・被相続人に対する侮辱、虐待、著しい非行 |
| 効果 | 相続権を失う | 相続権を失う |
| 代襲相続の有無 | あり | あり |
| 申立ての必要性 | なし(当然に欠格する) | ・被相続人が生前に裁判所に申し立て ・被相続人が遺言で廃除の旨を記載 |
| 戸籍への記載 | 記載されない | 記載される |
相続欠格にならない具体的なケース
相続欠格は、「相続に関して不当な利益を目的とするとき」に適用されます。
家族の関係から遺言書の存在を言い出せなかったとき
遺言書の存在を知っている唯一の相続人が、遺言書の存在を知らない法定相続人の話し合いの過程や関係性から遺言書の存在をなかなか言い出せないようなときは、「相続に関して不当な利益を目的とするとき」ではないので、欠格事由に当たらないとされています。
遺言書に欠けていた訂正印を押印する行為(最高裁昭和56年4月3日判決)
自筆証書遺言書に訂正箇所があるときは、当該箇所を二重線で削除の上押印し、「〇〇文字削除」といった文言を記載するなどして訂正削除を明らかにする必要があります。
この押印が欠けているものは訂正が無効となり、訂正されていないものとみなされます。
遺言書の訂正箇所に押印がされていなかった事案において、「相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないとき」であるとして、行為自体は遺言の変造にあたるものの、相続欠格には該当しないとされました。
相続欠格になる具体的なケース
遺言書に欠けていた日付を記載する行為(さいたま地裁平成20年9月24日判決)
自筆証書遺言書は財産目録を除く全文、日付及び氏名を自署することが要件であり、日付が抜けている遺言書は要件違背により無効です。
そして、この遺言書を有効にするために相続人が日付を記載することは、相続欠格の「遺言書の変造」に該当します。
これは先ほどの例でいう訂正箇所への押印と異なり、遺言書の有効無効そのものに影響するうえ、遺言書は作成日によってその結果が大きく左右されるものであるから、遺言者の意思を実現させるためその法形式を整える趣旨でしたものとみることはできず、相続欠格に該当するとされました。
遺言書を隠匿した行為(東京高裁昭和45年3月17日判決)
遺言者から遺言書の保管と不動産の遺贈を受けた相続人が、遺留分減殺(侵害額)請求を恐れて他の相続人に遺言書の存在を2年もの間隠匿し続ける行為は、相続人および受遺者の欠格事由たる遺言書の隠匿に該当し、相続欠格事由に該当するとされました。
相続欠格にする方法
ある相続人が相続欠格事由に該当しているものの、その相続人が相続欠格を認めないとき、裁判所に対して「相続権不存在確認請求訴訟」を提起します。
反対に、相続欠格を主張されている相続人は、自らの相続権を主張するために、家庭裁判所に「相続権確認請求訴訟」をすることができます。
相続欠格の注意点
要件に該当=直ちに欠格ではない
上の具体的な事例をみてわかるように、相続欠格が争われるのはほとんどが遺言に関する隠匿や変造のケースです。
相続欠格事由の要件に該当するからといって、問答無用で即座に相続権を失うわけではなく、欠格事由に該当する行為をするに至った経緯、理由、欠格事由該当行為が結果にどの程度影響しているのかによって変わります。
相続欠格が判明するタイミングで複雑に
相続欠格が相続の開始前、開始後遺産分割協議までの間に判明している場合は、相続開始のときに相続権を失うことになります。
一方、相続人同士が遺産分割協議を行ったあとに相続欠格行為が判明したとき、いったんは遺産分割協議により相続が確定してしまっていることから、相続欠格者が相続財産を占有していることが考えられます。
この場合には、真の相続人らは相続欠格者(相続人であるかのように振舞っている元相続人)に対して相続回復請求権を行使して、権利を取り戻すことになります。
欠格を公的に証明する書類はない
相続欠格に該当し相続権を喪失したことは、申し立てが不要でかつ戸籍にも記載されません。
相続欠格者自らが「相続欠格証明書」に署名押印するか、裁判所によって相続権のないことを確認する訴訟を提起することになります。