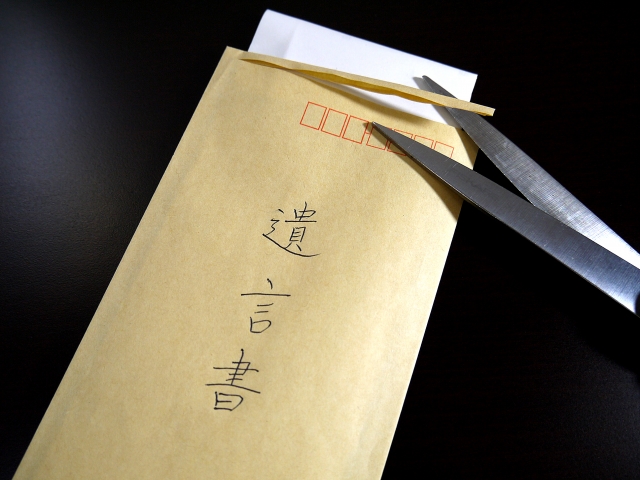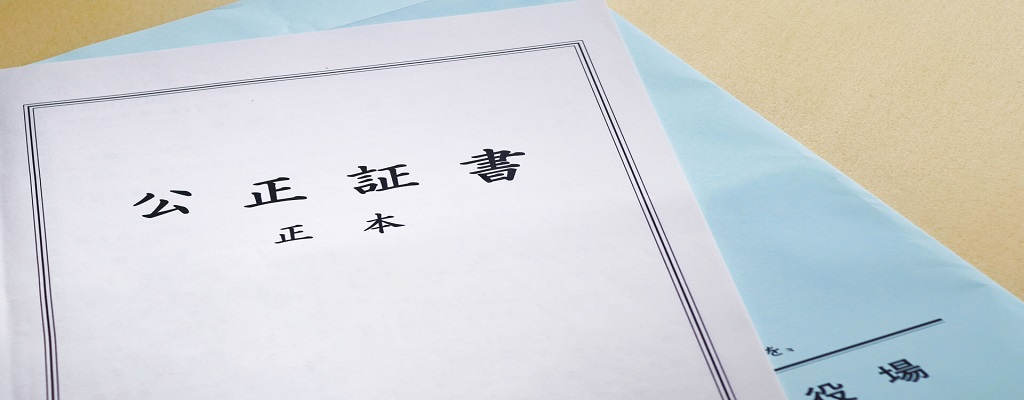遺言書の種類によっては、遺言者が亡くなった後に裁判所で検認手続が必要になる場合があります。
遺言書の検認手続についてご説明します。
遺言書の検認手続とは
裁判所で手続
遺言書の検認手続とは、相続人が裁判所で遺言の存在と内容を確認し、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして偽造や改ざんを防止するための手続です。
遺言者の死後に限られる
遺言書を作成した方(遺言者)が亡くなった後でしか、手続はできません。
相続人が裁判所に集まる
原則として遺言者の相続人全員が、遺言者の亡くなった後に、家庭裁判所に集まり手続をします。
検認手続が必要になる遺言書は?
公正証書遺言
公正証書遺言書は遺言書の検認手続は不要です。
遺言書の作成時点で遺言者本人に間違いないことを公証役場が確認しているためです。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書を自宅や貸金庫などから発見した場合は、裁判所で遺言書の検認手続が必要です。
自筆証書遺言書の法務局保管制度
自筆証書遺言書を作成した場合で、かつ法務局保管制度を利用している場合は、検認手続は不要です。
秘密証書遺言書
秘密証書遺言書も自宅で保管する自筆証書遺言書と同様に、検認手続が必要です。
遺言書の検認をするとどうなる?
裁判所の検認手続を終えると、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し保存します。
検認済みの遺言書があれば、遺言書の内容に従って不動産や預金の相続手続ができるようになります。
検認は必ずしなければいけない?
自筆証書遺言書は検認しなければ不動産や預金の相続手続をすることができません。
検認手続をする時期
検認手続をするのは、遺言者が死亡したあとに、遺言書の保管者(発見者)が遅滞なく行う必要があります。
遺言者が前もって検認手続をしたり、遺言者の生前中に相続人が手続をすることはできません。
検認手続にかかる費用
遺言書の検認手続は裁判所に申立てをするため、裁判所に提出する郵便切手や収入印紙代約5000円のほか、相続人を調査した戸籍謄本などの実費が約1~2万円かかります。
また、検認手続を司法書士など専門家に依頼した場合、約5万円程度の報酬がかかります。
検認手続にかかる時間
検認手続は、相続人の調査や必要書類の収集から、裁判所で検認を終えるまで約2か月~3か月かかります。
検認手続までの流れ
遺言書検認手続までの流れは、大まかに次のとおりです。
相続人調査
遺言書の検認のために、まず法定相続人を調査します。
具体的には、被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍・原戸籍と住民票などの住所証明書を取得します。
法定相続人については、存命であることがわかる現在の戸籍と住民票か戸籍附票を取得します。
裁判所提出書類を作成する
遺言書検認のために、裁判所に申立する書類を作成します。
申立書には遺言者の住所氏名生年月日のほか、遺言書を発見した日時や状況を記載します。
さらに、当事者目録として法定相続人の住所氏名を記載します。
申立人は一般的には相続人がなりますが、家屋の管理人や保管を任されていた人間も申立人になることができます。
家庭裁判所に遺言書検認の申立て
裁判所申立書類の作成ができたら、実際に裁判所に書類と必要書類を提出します。
管轄の裁判所は、遺言者(被相続人)が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所です。
戸籍などの原本は、申出をすれば還付をうけることができますので、その後の銀行や不動産の相続手続に使用できます。
検認期日が通知される
書類に不備がなければ、裁判所から各相続人に検認日の期日が通知されます。
検認期日当日
相続人全員(原則)が、検認期日に裁判所に集まり、遺言書の内容を確認します。
検認済み証明書の添付
裁判所が検認を終えたことの証明書と遺言書を合綴し、検認手続が終了です。
遺言書検認の注意点
検認済み=有効ではない
遺言書の検認手続は、後に遺言書の内容を改ざんされないようにするために、相続人が裁判所で確認し保存するための手続です。
裁判所が遺言書の有効無効を決めるわけではありません。
封がされている遺言書を開けても良い?
封がされている遺言書は、裁判所での検認手続のときまで開けることができません。
仮に開けてしまった場合は、5万円以下の過料に科される場合があります。
相続人は必ず出席しないといけない?
少なくとも遺言書を保有する相続人(ほとんどの場合は申立人)は出席する必要がありますが、その他の法定相続人は、出席できなくても手続が進みます。
検認済みの遺言書をなくしたらどうなる?
公正証書遺言書と異なり、自筆証書遺言書は検認を終えたからといって原本が裁判所に保管されるわけではありません。
検認済みの自筆証書遺言書を紛失してしまった場合は、裁判所で「検認期日調書謄本」を取得します。
検認期日調書謄本とは、遺言書の検認にあたって設けられた裁判所の検認期日の内容が記載された調書のことです。
調書に記載される内容は、担当した裁判官や出席した相続人の氏名、陳述した内容、検認された遺言書の状況(外観や内容)などです。
検認を経た遺言書は、偽造・変造防止のために、この検認期日調書とともにその写しが裁判所で保管されます。
この「検認期日調書謄本」で預金の解約や不動産の相続手続ができる場合があります。
遺言書に書かれた人が既に亡くなっているときは?
財産を受け取る相続人として遺言書に記載された人が、遺言者の相続開始時点で既に亡くなっている場合、その条項に限り遺言は無効になります。
遺言書全体が無効になるわけではありません。
遺言書に書かれた財産がなくなっているときは?
遺言書に記載された財産を、遺言者が生前に処分してしまっているような場合、その条項に限り遺言は無効になります。
遺言書に従って財産を取り戻したりできるわけではありません。
遺言書に記載された住所氏名が死亡時と違う
結婚等で遺言書を作成した当時の住所や氏名から変わっている場合、遺言書作成当時の住所氏名が証明できる戸籍や住民票などがあれば問題なく手続できます。
他の相続人に遺言書の内容を知らせたくない
検認が必要な自筆証書遺言書の存在を、他の相続人に知られずに手続することはできません。
自筆証書遺言書の検認手続の過程で、裁判所から各相続人に通知がされます。
遺言書の内容に従いたくない。納得できない。
相続人や財産の受遺者全員が同意している場合は、遺言書の内容に従うことなく遺産分割協議書を作成して相続手続を行うことができます。
遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の承諾も必要になります。
遺言書の筆跡や作成当時の本人の状況から、遺言書そのものの有効性に疑いがある場合は、遺言無効の訴えなどで有効性を争うことがあります。
検認手続のあとにすること
不動産の相続登記
検認済みの自筆証書遺言書に基づいて、不動産の名義変更(相続登記)を行います。
遺言書の内容によっては、財産を受け取る相続人だけでなく、相続人全員の協力が必要なケースもあります。
預金の解約
検認済みの自筆証書遺言書に基づいて、預貯金の解約払い戻しを行います。
複数の金融機関で手続をする場合、遺言書は1通しかないため、1金融機関ずつ順番に書類提出→解約→書類の返却を受けることになり、想定以上に時間がかかることがあります。
株式の相続
検認済みの自筆証書遺言書に基づいて、預貯金の解約払い戻しを行います。
株式の相続手続は、相続人が遺言者(被相続人)と同じ証券会社に口座を新規開設しないといけないことが多いため、相続することが予想できているのであれば先に口座開設をすすめていきましょう。
相続税の申告
相続税の申告が必要な方は、検認済みの自筆証書遺言書で取得した相続財産に応じて相続税の申告と納税をします。
申告期限は相続開始時から10か月以内ですので、検認手続が必要な場合はかなり迅速な手続が要求されます。
遺言書検認を司法書士に依頼するメリット
裁判所提出書類と相続手続に精通
相続手続は、司法書士だけでなく弁護士や税理士、行政書士が行うこともあります。
しかし、裁判所への書類作成を業務として行い、かつ相続の手続に精通している専門家は司法書士か弁護士のみです。
さらに、紛争性がないケースでは弁護士より司法書士に依頼する方が安価です。
不動産の相続登記をそのまま依頼できる
不動産の名義変更(相続登記)を行える専門家は司法書士のみです。
司法書士であれば、遺言書の検認からスムーズに不動産の相続登記に移行することができます。
依頼者の身体的、精神的負担が減る
遺言書の検認手続は、相続人調査(戸籍収集)に始まり、裁判所への申立書作成、期日に裁判所への出席と、相続人にかなりの負担がかかります。
しかも、役所や裁判所は平日しか開いていないため、仕事や日常に支障をきたすことも少なくありません。
専門家に依頼することで、これらの負担を最小限に抑えることができます。
相続を専門とする当事務所では、遺言書の検認申立てから裁判所との日程調整まで承っております。
戸籍など面倒な書類も全て当事務所が収集し、依頼者の手間を最小限にいたします。 ぜひお気軽にご相談ください。