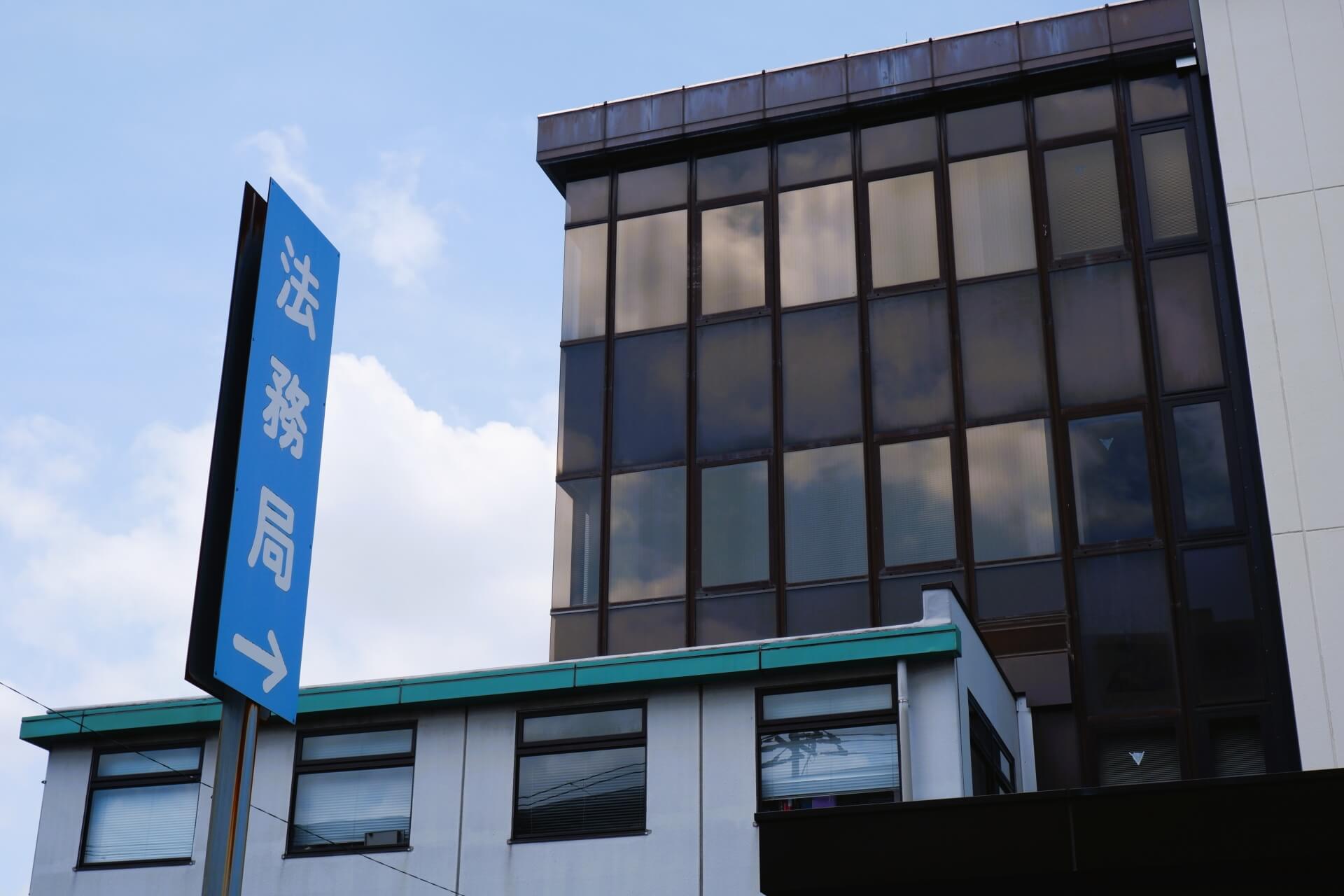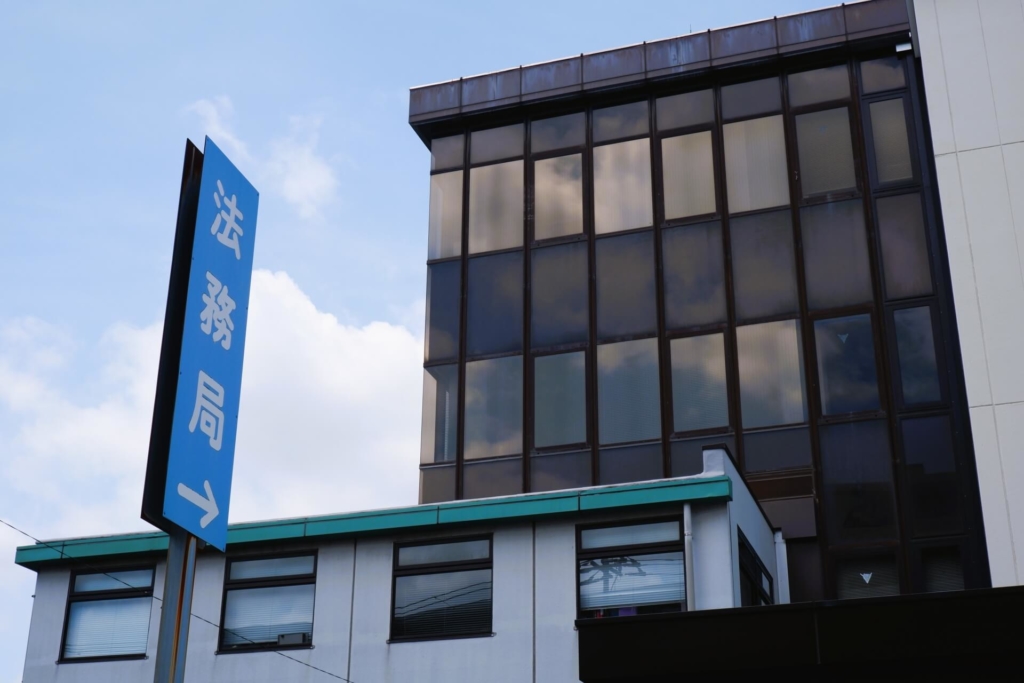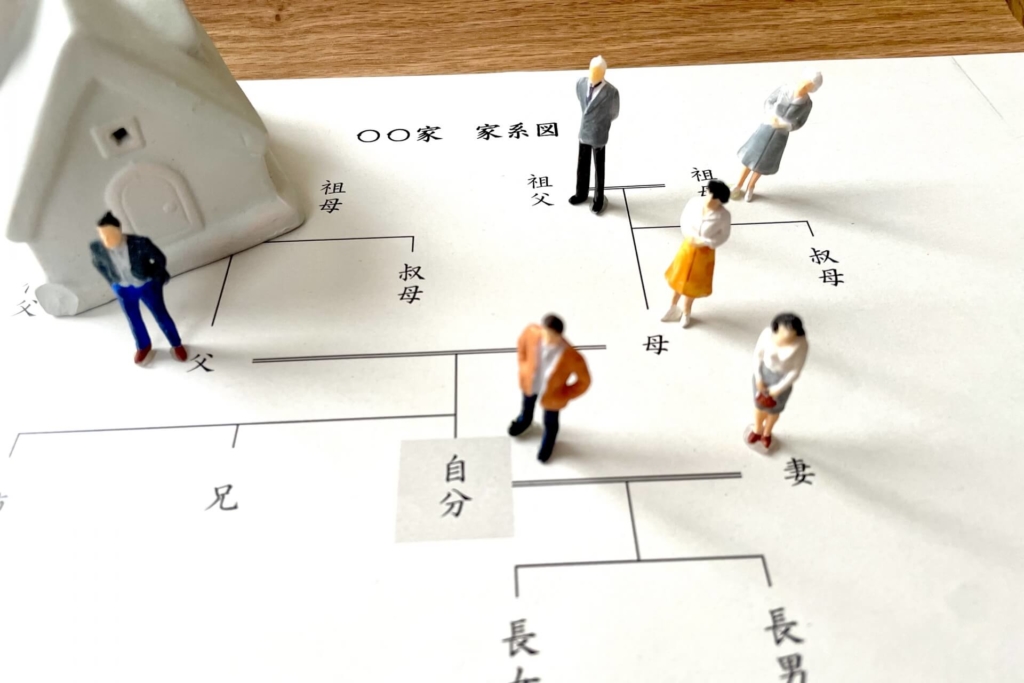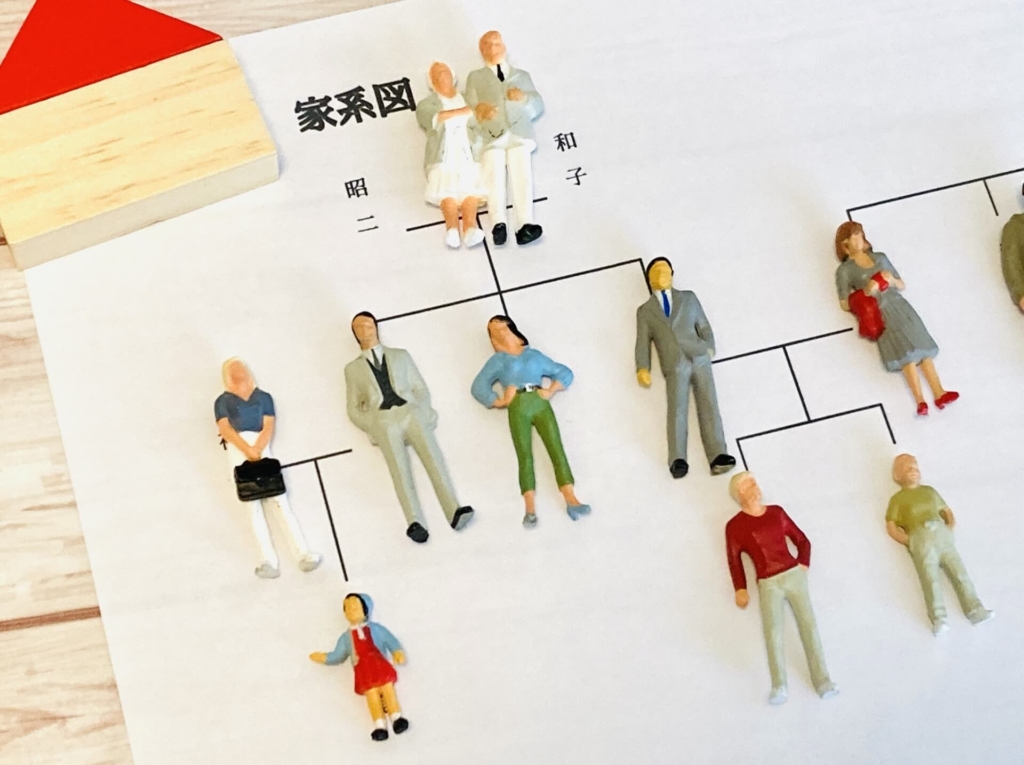自筆証書遺言書は法改正により法務局で保管することが可能になりました。
法務局で保管してもらう自筆証書遺言書は、通常の自筆証書遺言書で起きうるデメリットをなるべく排除して、遺言書作成をより利用しやすくするために設けられた制度です。
遺言者の自筆証書遺言書の情報を取得する手段として、相続人は遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書を選択します。
遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書の制度、利用できる人、請求方法、手数料などの費用、注意点などを解説します。
そもそも自筆証書遺言書の法務局保管制度とは?
近年の法改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言書の法務局保管制度によって、自筆証書遺言書のデメリットが改善され、遺言書自体のハードルが低くなり、利用しやすくなっています。
自筆証書遺言書の法務局保管制度については別記事で解説します。

遺言書保管事実証明書とは
遺言書保管事実証明書とは、その名のとおり「遺言書」が「保管されている(されていない)事実に関する証明書」のことで、法務局で遺言書が保管されている(もしくは保管されていない)場合に、その事実を証明してくれる書面です。
ただし、これは遺言書が存在するか否かを証明するだけの書面ですので、内容を把握したい場合は後述する遺言書情報証明書をあわせて請求することになります。
遺言書保管事実証明書を請求できる人
遺言書保管事実証明書を請求できるのは、遺言者の相続人、遺言執行者、受遺者(一般的に相続人ではないが財産を受け取る人)が請求することができます。
遺言書保管事実証明書を請求できる時期
遺言書保管事実証明書をいつ請求できるのかですが、遺言書を作成した遺言者が死亡した後に請求できます。
つまり、遺言者が存命である時に遺言書の有無を調べることはできません。
遺言書保管事実証明書を請求する法務局
遺言書保管事実証明書の請求先は、法務局は決まっていませんので、全国どこの法務局に対しても請求することができます。
遺言書保管事実証明書にかかる費用
遺言書1通につき800円の手数料がかかります。
これは法務局への請求時に収入印紙で支払います。
遺言書保管事実証明書で証明できる内容
遺言書保管事実証明書は、遺言書保管の有無を証明してくれる書面ですが、請求する人が相続人か相続人以外の人かによって意味合いが異なります。
具体的にまとめると次の表で場合分けができます。
| 遺言書が保管されている | 遺言書が保管されていない | |
|---|---|---|
| 相続人 | 申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていることを証明 | 遺言者に関する遺言書が法務局に保管されていない事実を証明 |
| 相続人以外(遺言執行者、受遺者) | 請求者を遺言執行者または受遺者とするなど、請求者に関係のある遺言書が保管されていることを証明 | 請求者を遺言執行者または受遺者とするなど、請求者に関係のある遺言書が保管されていないことを証明=請求者と関係のない遺言書は存在するかもしれない |
相続人以外の人が遺言書保管事実証明書を請求し、「該当する遺言書が保管されている事実がない」旨の証明書の交付を受けた場合、あくまで請求者に関係のある遺言書が存在しないことを証明しているだけで、遺言者が作成した請求者に関係のない遺言書が存在する可能性があります。
遺言書情報証明書とは
遺言書情報証明書とは、遺言者の住所氏名生年月日、本籍または国籍に加え、遺言書の作成年月日、法務局に保管されている遺言書の内容等を証明する書面です。
遺言書の原本は法務局で保管され、相続人に対して交付されることはありません。
その代わり、遺言書の原本を移した画像データを遺言書情報証明書として交付してもらうことになりますが、相続の手続はこの遺言書情報証明書で行えます。
遺言書情報証明書を請求できる人
遺言者の相続人、遺言執行者、受遺者等です。
直接遺言書に記載された相続人、遺言執行者、受遺者のほか、これらの相続人、相続放棄をした人、相続人の欠格または廃除を受けた人、信託の受益者なども請求することができます。
遺言書情報証明書を請求できる時期
遺言書情報証明書を請求できるのは、遺言書保管事実証明書と同じく遺言者が亡くなった後です。遺言者の存命中に相続人等が遺言書情報証明書を請求することはできません。
遺言書情報証明書にかかる費用
遺言書情報請求書の交付を受ける際にかかる費用は、法務局への手数料として1通につき1400円がかかります。
そのほか、郵送により交付を受けるときは郵送料にかかる郵便切手を請求書に同封します。
遺言書情報証明書の内容とできる手続
遺言書情報証明書は法務局に保管された遺言書の内容を証明してくれる書面です。
遺言書情報証明書があれば、銀行などの預貯金解約、不動産の相続登記、株式や年金の手続等に使用することができます。
遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書の違い
遺言書保管事実証明書と遺言書情報証明書は次のような違いがあります。
| 遺言書保管事実証明書 | 遺言書情報証明書 | |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人、遺言執行者、受遺者など誰でも | 相続人、遺言執行者、受遺者など |
| 証明される内容 | 遺言書の有無 | 遺言書の内容 |
| どんなときに請求する | 遺言書の存在自体が分からない | 遺言書の内容を知りたい |
遺言書保管事実証明書は、遺言書が存在するかどうかが分からない場合に利用する制度で、遺言情報証明書は、遺言書があることは判っており、その遺言書の内容を知りたい場合に請求する点で違いがあります。
遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書の注意点
法務局の窓口で請求する場合は予約必須
法務局に遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書を請求する方法は、窓口での請求と郵送での請求がありますが、窓口で請求する場合は事前に予約が必要です。
遺言書保管事実証明書でわかるのは法務局保管の遺言書の有無だけ
遺言書保管事実証明書は法務局に保管されている自筆証書遺言書が存在するか否かを証明してくれるだけですので、法務局保管以外の遺言書、つまり公正証書遺言書と、自宅で保管する遺言書の有無は別途調査することになります。
遺言書を司法書士に相談するメリット
公証役場との打合せを任せられる
専門家に公正証書遺言の作成を依頼すれば、専門家が公証役場との連絡や打合せまですべて行いますので、遺言者の負担を減らすことができます。
法的に有効な遺言書を専門用語を使用して作成してもらえる
どんな遺言書を作成したいか伝えるだけで、専門用語を使用した法律的に有効な遺言書案を作成してもらえます。
二次相続、遺留分、相続関係など今後の法的リスクも相談できる
遺言書を残すことで相続人同士の相続関係や二次相続、遺留分にどのような影響があるかまで、将来のことを見据えた専門的なアドバイスを受けることができます。
税金対策に着手できる
相続税がなるべくかからないように、税理士などの専門家と協力して有益な税金対策に着手できます。
相続の専門家である当事務所なら、公正証書遺言書の作成について、適格に法的なアドバイスができます。また、税金の問題点については税理士とともにアドバイスできますので、安心してご相談ください。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。