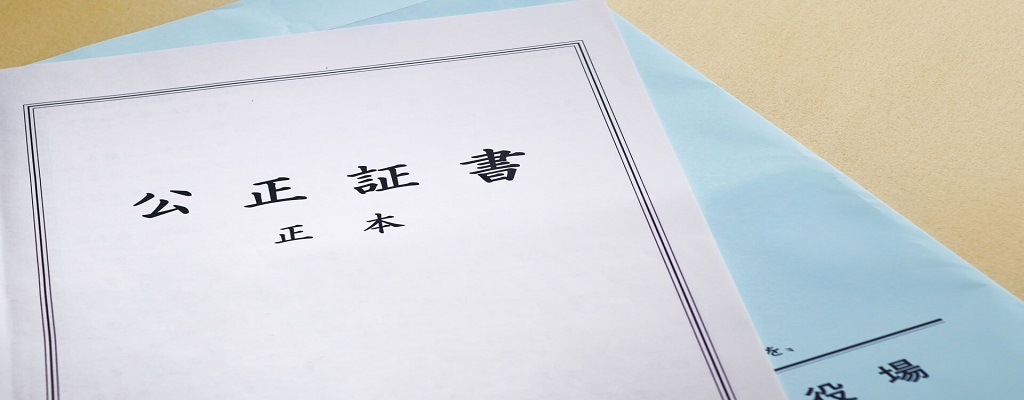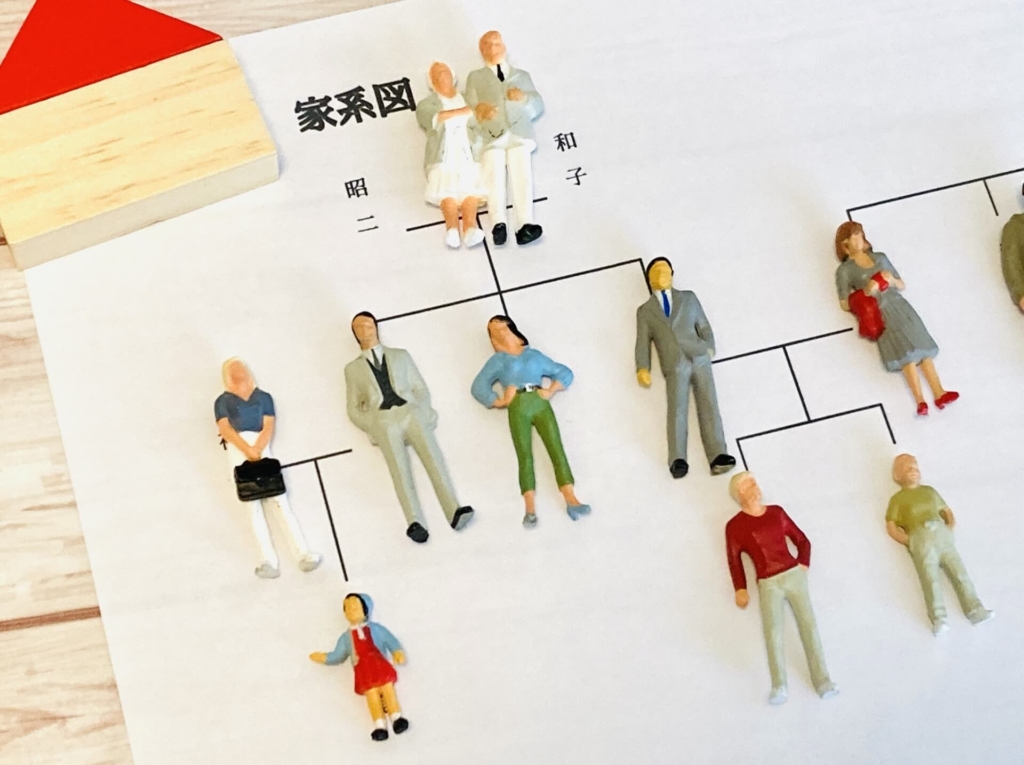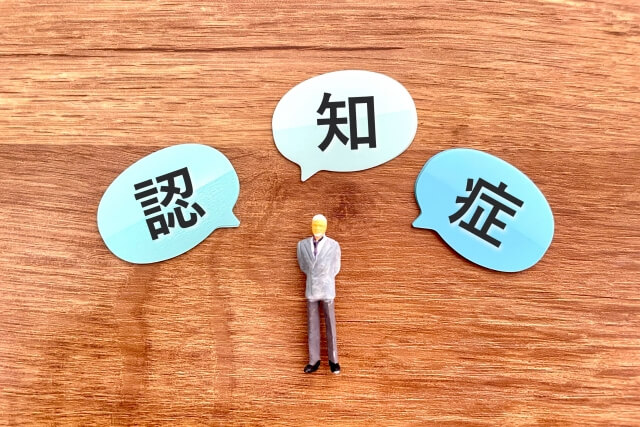有効な遺言書が作成されているとき、相続手続は原則として遺言書に沿って行われます。
そのため、相続人の全員による話し合いである遺産分割協議が不要になりますが、遺言書があっても遺産分割協議が必要になることもあります。
遺言書がある場合は遺産分割協議が不要になるのか、必要なケースや注意点を分かりやすく解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合いによって、誰がどの財産をどの程度相続するかを決定することです。
遺産分割協議は相続人が複数いる場合に分割方法を話し合うために行いますので、相続人が1名しかいないときは遺産分割協議がそもそも必要ありません。
遺言書がある場合の遺産分割協議
原則は遺産分割協議が不要
遺言書がある場合、遺言書には「全財産を○○に相続させる」「不動産をAに相続させる」といったことが記載されています。
この場合、「誰が何をどれだけ相続するか」を予め遺言者(亡くなった方)が指定している状態であると考えられますので、相続の手続は原則として遺言書に記載されたとおりに進めていくことになります。
つまり、遺言書がある場合は相続人全員での遺産分割協議が不要となり、遺言書に従って相続手続を進めていきます。
遺言書があり遺産分割協議が必要なケース
遺言書がある場合は遺産分割協議が原則として必要ありませんが、次のようなケースでは遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書が無効
様式違反
遺言書は大きく分けて自筆証書遺言書と公正証書遺言書があります。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書はそれぞれ有効に成立するための要件が決まっており、その要件を欠くと無効になってしまいます。
無効になった遺言書では相続手続が行えないため、遺言書が存在しないものとして相続人が遺産分割協議を行うことになります。
受遺者が先に死亡している
遺言書に記載された財産の相続人や受遺者が、遺言者よりも先に死亡している場合、その部分については遺言書が無効になってしまいます。
例えば、Xが作成した遺言書の中に「不動産1をAに相続させる。」という文言があり、AがXよりも先に死亡している場合、不動産1については相続人全員が遺産分割協議を行って相続手続を行うことになります。
受遺者や相続人が放棄した
特定の財産を相続人以外の人に遺贈した場合、受遺者はその遺贈を拒絶することができます。
また、相続人や全財産を相続させると指定された相続人以外の人は家庭裁判所で相続放棄をすることができ、相続放棄をすると遺言書に記載された財産を受け取る権利を失います。
このように、財産の承継で指定された相続人などが相続放棄をすると、遺言書が実質的に無効になってしまい、相続人全員の遺産分割協議が必要になります。
遺言書に記載のない財産がある
遺言書は、遺言書に記載のある財産についてのみ効力を発揮します。
「全財産を相続させる」「遺言書に記載のない財産も含む」などと包括的な文言が記載されていない限り、遺言書から書き漏らしてしまった財産は通常どおり相続人全員の遺産分割協議をもって相続手続を行います。
また、遺言書に記載した財産が誤っている場合、例えば不動産を地番ではなく住所で記載していたり、銀行の口座番号の書き間違い、銀行の記載漏れなども、遺言書から漏れてしまった財産として扱われてしまいうため、注意が必要です。
遺言書に従わない相続の分割をしたい
遺言書が存在している状態でも、相続人の全員が遺言書に従わず遺産分割協議をすることができると解されています。
相続人の全員が遺言書の内容ではなく、別の分割方法にしたい場合は、遺産分割協議書を作成して相続手続をします。
ただし、相続人以外の受遺者がいるときはその受遺者の承諾、遺言執行者がいるときは遺言執行者の承諾が必要です。
遺言書があるメリット
遺産分割協議が原則として不要
遺言書がある相続手続は、相続人全員による遺産分割協議が必要なくなります。相続人の話し合いが必要な相続手続は、相続人同士の意見が合わずにもめてしまう事があります。
遺言書があると、もめてしまう要素の1つである相続人同士の遺産分割協議を省略できるため、相続手続が途中で止まる可能性が低くなります。
未成年者、認知症、海外在住者に影響されない
相続人のうち、未成年者、認知症の方、海外に在住する方がいる場合、相続手続の中で裁判所に申立をする必要が生じたり、外国の領事館に行ってもらう必要があるなど、かなり大変です。
遺言で先に財産を相続する人を指定しておけば、裁判所の手続や領事館での書類の授受を省略できることがあります。さらに、遺言を遂行する執行者を指定すれば、本来は相続人全員の協力が必要な手続が、遺言執行者1人のみで可能になります。
収集する戸籍や書類が少なくなる
遺言書がある相続手続は、必要となる戸籍や印鑑証明書などの書類の数が減ります。
その結果、費用を削減することができますし、管理や提出を簡略化できます。
相続手続にかかる時間が短縮される
相続は、銀行、株式、不動産、自動車など様々な財産の手続を1つずつ行うことになりますが、遺言書を用いた相続手続は書類の数が少なく、更に遺言書で予め相続する人が決定されているため、時間が大幅に短縮できます。
司法書士や弁護士に遺言書の保管、執行を任せられる
遺言書の作成段階から司法書士や弁護士などの相続の専門家にご相談いただければ、事務所で遺言書の保管を行ってもらうことができます。遺言書の紛失、盗難リスクが減るだけでなく、相続人が生前に見つけてしまう心配や、相続人が遺言書を改ざんする心配もありません。
さらに、司法書士や弁護士であれば、遺言者が亡くなった後は遺言書の存在を相続人に通知し、そのまま手続を行うことができます。